
2018年11月1日よりタイトルをWCA(世界の時事)に変更しました。
「タワケ」
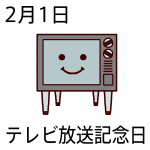 元寇に際して、鎌倉武士たちが国家の防衛のための戦いをしたことについて、これを「必要なかった」という人は、まずいないと思います。
元寇に際して、鎌倉武士たちが国家の防衛のための戦いをしたことについて、これを「必要なかった」という人は、まずいないと思います。
戦って撃退しなければ日本は元の支配下となるだけでなく、壱岐対馬の島民たちの惨劇は、そのまま日本本土の惨劇となっていたのです。
ロシアに「白ロシア」という地名がありますが、これは「ベラ・ルーシュ」を訳した地名です。「ベラ」が白、「ルーシュ」はロシアを意味します。
その「ベラ」には、もうひとつ「処女」という意味があります。
なぜ「処女」なのかというと、このあたり一体が湿地帯であったため、馬で移動するモンゴルの軍隊がこの地を避けて通ったことによります。
おかげでこの地の女性たちの純潔が守られたから「ベラ」です。
戦争はいけないことです。
けれど近現代の国際社会においてさえ、挑発(Provocation)を受けて攻撃(Attack)することは、国家の正当な自衛権の発露です。
まして挑発どころか、一方的に攻撃(Attack)してきたものに対して国家が民を守るために戦うことは当然のことです。
なぜなら戦わなければ、戦って死傷する人たちよりも、もっと大きな悲惨が生まれるからです。
ちなみに主権という概念は、ヨーロッパ諸国がもともと暴力社会であったことに由来します。
誰もが誰もと敵対し、誰もが常に危険にさらされている。
敗れれば個人の誇りも貞操も、ありとあらゆるものが蹂躙されるのです。だから身を守るために民衆が王の庇護のもとに入り、王が交戦権者となりました。それが主権者のはじまりです。
元寇に話を戻します。
最近の教科書などには、「二度にわたる元寇のあと、鎌倉幕府は、文永、弘安の役に対する御家人への恩賞が不十分だった(外国からの防衛戦だったために恩賞を与える土地がなかった)ために、鎌倉幕府は外国からの侵略は防げたが、御家人の生活を守れなかった。このため鎌倉幕府は御家人たちの不満が募り、滅亡した」などと記述しているものがみうけられのだそうです。
本当にそうなのでしょうか。
そもそも鎌倉幕府の滅亡は1333年です。これは弘安の役の五十二年後にあたります。半世紀経過しているということは、元寇と鎌倉政権の滅亡には、因果関係はないということです。
なるほど鎌倉政権崩壊後、政権自体は源家(実権は北条家)から足利家に移りましたが、その後1868年の明治政府樹立まで、長い武家政治の時代が続いています。
鎌倉幕府は滅んだけど、征夷代将軍が交替しただけで、武家政権そのものは、元寇のあとも、まる六百年続いたのです。
つまり武家政権そのものが持つ信用は、鎌倉政権崩壊後も社会に保持されたのです。
ではなぜ鎌倉幕府が崩壊したかというと、それには別な理由があります。相続制度です。
鎌倉武士たちの相続制度は、いまの日本と同じ均等配分方式です。子供が5人いれば、財産は5等分されます。実はこのことは、はたいへんな問題をはらんでいます。
鎌倉武士というのは、先に書きましたように、もともとは平安時代に生まれた私有地(新田)の開墾百姓です。それが長い年月の間に、広大な領地を保有するようになりました。
彼らはその領地で、一族郎党を養い、その領土を武家の棟梁(とうりょう)である幕府に安堵してもらうという御恩を受け、その御恩に対するお礼として、一朝ことあればいざ鎌倉へと出陣する、つまり「御恩と奉公」の関係を持っていました。
その領地は、それぞれの武家の「家」を単位にまとまっています。ですから子がいなくて「家」がなくなってしまっては、安堵してもらう領地があっても、安堵してもらう人がいなくなるわけですから、一族郎党が土地を失い、みんなが飢えてしまいます。
つまり彼らにとって、子を残すということは、たいへん重要なことだったわけです。
ところが昔は、子供は、たいへんよく死にました。いまでこそ、一人っ子でも、ほぼ全員が成人を迎えることができますが、ひとむかし前までは、子が成人できるということ自体が、めずらしいことといってもいいくらい、たいへんなことでした。
ウチの死んだ祖母は明治の終わりごろの生まれですが、四人の男子を産み、そのうち二人が幼くして病没しています。昭和のはじめですらそうなのです。
江戸時代の後期、桜田門外の変で殺害された大老・井伊直弼は、井伊家の十四男坊です。
長男が家督を継ぐ時代に、なぜ十四番目の男の子が家督を継いだかといえば、別に彼がとびきり優秀だったからということではなくて、一番めから十三番目までの井伊家の子たちが、みんな病没したからです。
それくらい昔は、子を大人に育てるのはたいへんなことだったのです。だから子供が三歳、五歳、七歳になると、よかったよかったといって、お祝いをしたのが七五三です。
まして鎌倉時代が崩壊した頃というのは、井伊直弼の時代より六百年も昔です。子が成人するだけでも困難な時代に、御家人たちが家を保持するためには、それなりに子をたくさんもうけなければなりません。
当然子だくさんになる。その中で、生き残って成人した幾人かが家督を相続します。ところが、ここでの相続が、実は「均等配分方式」だったのです。
するとどうなるかというと、仮に百人を養えるだけの土地があり、子が二人だったとすると、最初の相続では、子が二人なら、50,50に土地が分割されます。これが二代目です。
三代目になると、25になります。
四代目になると、12.50
五代目になると、 6.25
六代目になると、 3.00
七代目になると、 1.50
八代目になると、 0.75
つまり、七代目にはもう夫婦で食べて行くことすらできず、八代目になると、自分ひとりさえも食べられない。家が崩壊してしまうわけです。
この時代、元服も結婚も早かった時代ですから、一世代はおよそ20年で交替しています。
つまり20年×7代=140年で、見事財産が崩壊します。
実際、鎌倉幕府は数式通りに141年目に崩壊しています。
田んぼを均等に分けて財産相続することで、、国を滅ぼし、家を滅ぼすことを、後年の人は嗤って、これを「田分け(たわけ)」と呼びました。
よく時代劇などに出て来る「たわけものめがっ!」の「たわけ」です。
鎌倉幕府は、こうした相続制度の欠陥による御家人たちの窮乏に対し、開幕から105年目の1297年(相続四世代目)のときに、「徳政令」といって、御家人たちの借金帳消し令を発布しています。
けれどこれは今風に言えば、破産宣告です。
現代社会でもそうですが、破産宣告を受けたら、もう借金はできません。「田分け」によって、借金しなければ生活できないのに、借金ができないのです。これはたいへんなことです。
こうして鎌倉幕府は、政権運営主体としての信用を落とし、結果として1333年に崩壊してしまうわけです。
鎌倉幕府の崩壊は元寇とは因果関係がないと書きました。
実際その通りで、江戸時代の武士たちにとっても、最大の褒め言葉は「お主はまるで鎌倉武士のようだ」というものでした。
外敵と戦って見事に国を守り抜き、誇り高く立派に生きた鎌倉武士は、時代を超えて人々の憧れの対象だったのです。
しかし、いくら高い誇りを胸に抱いていても、食べなければ人は生きていけません。
相続制度の根本的問題点によって、武士たちの生活が困窮すれば、武士たちはお金をつかわなくなります。武士がお金を使わなければ、商業は沈滞化します。商業が沈滞化すれば、モノの値段が下がります。当然、農業生産物の値段も下がります。
そうなると農家の生活はますます苦しくなります。
つまりデフレです。
こうしたデフレに陥った世間をなんとかして経世済民のためにと立ち上がったのが、後醍醐天皇です。
これが「建武の中興」です。
ちなみに「経済」というのは隋代の儒学者の王通(おうつう)が書いた「文中子(ぶんちゅうし)」という書物の中に出てくる「経世済民」が元です。
後の世の幕末に英語の「Economy」の翻訳語にあてられるまでは、経世済民は、政治経済や行政司法立法などの政治全般を指す言葉でした。
そもそも鎌倉幕府は、天皇が認証を与えることによって成立している政権です。その鎌倉政権が、事実上崩壊してしまったというなら、誰かが幕府にかわって政治の指揮をとらなければなりません。
私は、個人的には、後醍醐天皇というのは、もったいないことですが、とても責任感が強くて、また勇気があって、人間味豊かな天皇であったろうと思うのです。
と申しますのは、後醍醐天皇は、鎌倉幕府崩壊にともなう社会の混乱に、幕府を親任し、その権力に裏付けを与える存在であるべき天皇自らが、親政(しんせい)というカタチで政治の指揮を執ろうとなされているからです。
「親政」というのは、たいへんわかりやすい言葉です。権力に認証を与えた「親(天皇)」が、「子(幕府)」にかわって直接政治の指揮を執るという言葉だからです。
後醍醐天皇は、政治の指揮を執り、全国で分割されてしまったすべての農地を、いったん古代律令国家の体制に戻すことを宣言されました。
古代律令国家の体制というのは、公地公民制です。
つまり、均等配分方式の相続によって寸断され、細分化されてしまっているすべの田畑を「公」のものとする、と宣言されたのです。
このことをもって後醍醐天皇が鎌倉幕府の倒壊を仕組んだと解説している本が数多く見られますが、それは違うと思います。
なぜなら後醍醐天皇は、この改革を行うに際し、元号を「建武」としているからです。「建武」とは、「武士の世を建てなおす」という意味です。
後醍醐天皇の大御心にあったのは、いったんは日本の姿を七世紀の古代律令体制の姿に戻し、相続制度を見直して経世済民を立て直した上で、あらためて「武」を建てる。
つまり武家に政権を委ねるという大御心であったのです。
後醍醐天皇の大御心には、明らかに混乱した民の窮状をなんとかしなければという動機があります。
だからこそ、後醍醐天皇のもとには、楠正成や児島高徳など、心がきれいで忠義心が強く、経済的にも比較的豊かな忠臣たち集いました。
ところが思わぬところで後醍醐天皇に障害があらわれました。
それは同じ朝廷内に、後醍醐天皇の行動に、疑念を持つ人たちが出てきたということです。
どういうことかというと、まさにそのことが、わが国の天皇という存在の本質なのですが、要するに「天皇親政」つまり、天皇が直接政治の指揮を執るということは、天皇が政治権力者、もっというなら、ただの「大王」の位置にまで降りてきてしまうということを意味するのです。
わが国における天皇という存在は、世俗にまみれた「政治」というものよりも、もっとずっと高位な位置にある存在です。
天皇は、わが国の最高神である天照大神から綿々と続く神の直系の子孫です。
その神の血統が、民衆の親となり、その親が政治を行う者に認証を与えます。
だからどのような政権下においても、天皇は神聖不可侵の存在ですし、一般の民衆は、天皇の民、すなわち公民(皇民)となることで、権力者による支配と、それへの隷従という奴隷的支配関係から解放されています。それがわたしたちの国の基本となる形です。
ところが、後醍醐天皇が親政を行うということは、天皇がその政治権力者の地位にまで降りてしまうということになるわけです。
こうなると民衆は天皇の私有民です。
土地もです。つまり公地公民ではなく、私有地私有民制になってしまうのです。
聖徳太子の御治世における十七条憲法においても、第一条は「和をもって尊しとなす」です。
つまり民の幸せ、民の安定、民の和が、第一条です。仁徳天皇も、かまどの煙の逸話にあるように、念頭にあったのは常に民の安寧です。
そしてそのためにこそ、古来わが国では天皇は、政治的権力と切り離した、もっと上位の存在とたのです。このことがわが国の民が私有民として奴隷的支配をされないでいる民の幸福の根源的存在です。
このような社会構造を大切にしたからこそ、古来、天皇みずから政治を行おうとするときは、天皇はその位を子に譲って、子から上皇という位を授かって院政(いんせい)を行うといった、やっかいなことをしているわけです。
もし後醍醐天皇が、子の成良親王(なりよししんのう)に皇位を譲って院政をひくか、あるいは成良親王を、鎌倉幕府の将軍に任命して、成良将軍のもとに政治を行おうとしたのなら、建武の中興は、多くの臣官の賛同を得て大成功となり、その後の長い治世を築く土台となったかもしれません。
後醍醐天皇は、そうした日本古来の伝統的統治の体制と、いま目の前にある民の窮状との板挟みのなかで、ご自身でいま目の前にある民の窮状を救うという選択をなされました。
けれども結局後醍醐天皇の建武の中興は、それが天皇親政というカタチをとったがゆえに、これを拒否する多くの人たちの反対によって、持明院統の別な天皇(北朝)が生まれます。
明徳三(1392)年、明徳の和約(めいとくのわやく)によって、後小松天皇に皇位が譲られ、もとの日本古来の天皇の認証による権力者という社会形態に戻るわけです。
たしか司馬遼太郎の文芸春秋の冒頭言だったと思うのですが、友人の作家が「太平記」を書こうとしていることに触れ、
「あの時代はまさに権謀術数渦巻いた時代で、その時代を書こうとすると、たいていの人は頭がおかしくなってしまうので、やめたほうがいいと話した」と書いていたことがあります。
「太平記」は、室町時代に書かれたとされる本で、現存するものが全四十巻もある大長編です。
後醍醐天皇の即位から鎌倉幕府の滅亡、建武の中興の失敗と南北朝分裂、南朝の怨霊の跋扈による足利幕府の混乱までを描いた物語です。
原典があるわけですから、源氏物語や義経記のように、現代版の小説になりやすそうです。にもかかわらずなぜ太平記を扱うと「頭がおかしくなる」のかというと、その時代が権謀術数渦巻く時代だったからだと解説されます。しかしもしそうなら、逆に小説としてはおもしろい題材です。
実は、太平記の時代を扱うと、どうしても「天皇とは何か」という問題に触れなくてはならないのです。
司馬遼太郎の時代は、戦後の復興期にあたります。この時代、日本の社会が戦前の常識を取り戻そうとすることは極端に否定されました。いまではまるでおとぎ話のような話ですが、この時代、日本が国産の飛行機を作ろうとしただけで、連合国(United Nations)に楯突く兆しあり、ということで日本は再占領下に置かれる可能性すら否定できなかった時代です。
それだけに司馬遼太郎の歴史小説などは、乃木大将を否定したり、実際の史実とは、かなり様子の異なる「戦を仕掛ける戦国大名たち」を強調したりしていますが、それでも大流行の人気作家であったことは、氏の力量のなせるわざであったものと思います。
太平記を小説化しようとすると、どうしても、なぜ朝廷が南北に分裂したか、そもそも天皇とはなんぞや、という議論にどうしてもいたらざるを得なくなります。
そこを明確にしなければ、小説になりません。だからこそ朝日に近かった司馬遼太郎は、それをわかって、友人の作家に、「太平記はやめとけよ。メディアから閉めだされるぞ」と言ったのではないでしょうか。
いまでもこうした言論への「潰し」活動はさかんに行われています。これは、本来自由であるはずの学会でも同じです。
たとえばナチスドイツのアウシュビッツにおけるユダヤ人の虐殺は、ヨーロッパでは戦後、それをあったとする学者さんたちと、なかったとする学者さんたちで、激しい言論戦が展開されています。内容的には、なかった派の方が、やや優勢です。
けれども日本国内では、なかったという議論があるということさえも、まったく報じられないし、学説の翻訳もされません。
あったかなかったかの議論さえ、知らされません。
まったく「あった」という先入観に凝り固まってしまっている、もしくは「なかった」という意見の存在さえも知らないのは、現在、世界の中で日本人くらいなものです。