
2018年11月1日よりタイトルをWCA(世界の時事)に変更しました。
「日本の包丁」
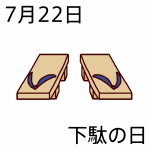
なぜ外国人シェフは「日本の包丁」に惚れ込むのか
これは柳刃包丁。ご存知、魚を刺身にするのに使う包丁だ。和包丁は用途によって200ほどの種類がある。プロはそれらを使いわけ、目指す味をつくりだす
国際社会における日本の影響力の低下がいたるところで説かれるが、こと料理業界について言えばそれは必ずしも当てはまらない。日本料理人は世界から引っ張りだこで、海外から日本に料理を学びにくる人も増加している。一昔前であれば考えられないことだ。
もちろん金額が違うので、一概な比較はできないのだが、家電をはじめ、日本製品が売れない、という悲観論が囁かれるなか、例えば包丁は財務省が出している貿易統計によると、台所用刃物の輸出額は04年以降(リーマンショックのあった年を除き)右肩上がりの成長が続いている。
かつては海外の星付きレストランのシェフたちが来日すると、包丁を何本も買い込んで本国に持ち帰る光景が見られたが、今ではごく当たり前のように誰しもが日本の包丁を使う時代になった。
プロ用和包丁シェア90%の堺市
職人の分業で成り立つ包丁づくりの世界
世界のシェフが日本の包丁を認めている理由は、やはりその切れ味だ。例えば刃物で世界的に有名なドイツ、ゾーリンゲンのツヴィリングJ.A.ヘンケルス社は最高級ラインの商品を製造する工場を、岐阜県関市につくっている。最高の切れ味を実現するには日本の職人の技術が必要だったからだ。
ドイツの会社のフラッグシップモデルである洋包丁が日本で製造されているということは、業界外の人にはあまり知られていないかもしれない。
さて、洋包丁の話は横に置いておいて、日本料理の料理人が愛用する和包丁の産地は大阪、堺市である。堺市の刃物の全国シェアは約7%と小さいが、プロ用の和包丁に関しては90%以上のシェアを誇っている、という話だ。
今回は包丁づくりの実際を見学するために、堺市にある和泉利器製作所を訪れた。和泉利器は堺刀司ブランドの刃物で知られた1805年創業の老舗である。日本の包丁の産地には高知、福井、岐阜、新潟などがあるが、一部以外ほとんどが分業生産を行っている。堺の包丁づくりも鍛冶、刃付け、柄付けと製造工程が分業化されているのが特徴だ。
ここで堺の包丁の世界について説明しておきたい。
先に説明したように堺の包丁づくりは分業制で行われている。
鍛冶屋:鉄から包丁を生みだす作業だ。火の力を使い鉄を鍛造し、おおまかな形をつくる。
刃付け屋(研ぎ屋):鍛冶屋からあがってきた包丁の形のものを、研いで刃を付けるところ。
柄屋:柄を製造する場所
卸し:卸屋は包丁を小売店に卸すだけではなく、柄つけや仕上げなど商品にする作業を担当。ここで包丁メーカーなどの銘を切ることもある。
職人の目は炎の色で鉄の温度を見抜く
包丁は外から見ただけではこれをが誰がつくり、どのような道をたどって手元にきたのか、わかりづらい商品だ。別のところで聞いた話だが、外国で製造したものを堺市で刃付けだけおこなっている、というケースもあるという。包丁メーカーの銘柄は切られているが、それだけではどこの誰の手を渡ってつくられたものかわからない。どのような経緯でこのような形になったのか? 僕が理解した範囲では慣習として思えず、詳しいことはわからない。包丁の流通は──あくまで僕の目から見ればということだが──不思議だ。
機械のように正確な職人の目が
炎の色で鉄の温度を見抜く
明治創業の池田刃物製作所は住宅街のなかにある。市内各所に小さな事業者が点在していることも、堺の包丁作りの特徴
製造現場を専務の信田尚男さんに案内していただいた。専務の信田尚男さんの案内で訪れたのは池田刃物製作所。池田さんは、ここで『鍛冶』の工程、刃付け前の本体部分をつくっている。
鍛冶の工程は11あまりにわかれているが、材料としてはすべて鋼でつくられている『本焼き』と軟鉄に鋼をあわせ『あわせ』の二種類に分類できる。当然、『本焼き』のほうが高価だ。
池田さんがハンマーを下ろすと、火花が散る。燃料はガスを使っているが、昔ながらコークスのほうが温度調整はし易い、とのこと。ただしコストがかかるそうだ
今回はあわせの包丁をつくっているところを見せていただく。釜の炎で工場は熱に満ちている。ハンマーで叩くたびに、火花が散る。あわせは硬い金属と柔らかい金属を接合する日本独特の技術だ。
刃物は硬いほうが切れ味が良い。しかし、硬いということは脆さと背中合わせだ。あわせというのはそこに柔らかい金属をつなぎ合わせることで、その弱点を補い、刃先を鋭くしながらも、折れたり割れにくくする、という技術なのである。この作り方は不思議なことに諸外国では見られない。
「温度が重要、熱くなりすぎると刃が駄目になってしまう。かといって、温度が低すぎると硬くならへん」
──その温度はどうやって見分けるんですか?
「色やね。炎の色や。本焼きとあわせでは温度が違うんやけど、色で800度なのか1000度なのか、見ればわかる。あわせは900度ではひっつかない。1100度になると、鈍ら(なまくら)になってしまう。950度から1050度のあいだで叩いて、2つの金属をくっつけるわけや」
目で見ることが必要なのは、炉の温度は計ることがわかっても、入れている鉄の温度ははかれないからだ。温度計で判断していたのでは「鉄は熱いうちに打て」の言葉通り、機を逃してしまう。
「困るのは、ぼくは時間があるときは日本刀もつくるんやけど、あれは材料が玉鋼やさかい、全然違うねん。だから、一度日本刀をやってしまうと、目が戻るのに少し時間がかかる。その時は調整が必要なんよ」
別のものをつくった後には、パソコンのモニターのキャリブレーション(色調整)のような作業が必要とは思わなかった。それほど職人の目は機械のように正確に温度を見極める。池田さんは十度単位で温度を見極めることができるそうだ。
世界からの注目度と反比例して衰退する包丁産業々
科学的には金属は最も硬度が得られる温度よりも若干低い温度で加熱することで、粘り(靭性)が得られる。前述した通り、硬いほうが切れ味は良いので、粘りはそれとのトレードオフ、ということになる。その見極めは非常に繊細なものだ。
「和包丁の需要は減ってきましたな。私らが若い頃は注文が一杯入ってきて、ずっと打ってましたもん。そのときはみんな『本焼き』職人さんもええものを使おておりました。もう少し歳をとったら日本刀つくりに専念したい。刀は面白いでっせ」
世界から注目され輸出も増えている和包丁だが、国内の需要は減少傾向にある。
世界からの注目度と反比例するように
衰退傾向にある包丁産業々
そうして池田さんがつくりあげたものを、今度は研師が仕上げていく。紹介していただいた森本さんは「現代の名工」にも選ばれている職人である。作業場はさらに狭く、人が一人通ればやっとの通路の両側に、研ぎのための道具が並ぶ。
「ほな、はじめましょう」
森本さんによる研ぎの作業。ここに並んでいる機械もすべて研ぎ師の手によるもの。道具をつくるところから仕事がはじまる
重みのある口調で森本さんは研ぎの工程を一つ一つ説明してくれる。研ぎの工程は荒研ぎから仕上げまで20以上にわかれているそうだ。それぞれの工程を経るたびに、包丁は鈍い輝きを増し、美しくなっていく。注目したのはひとつひとつの工程を経るごとに歪みを矯正していくことだ。
「鍛冶屋さんがつくってくれたものにはまだ荒いんですな。合わせの場合は金属の性質上、硬いものと柔らかいものが引っ張り合うので、歪みやすいわけです。包丁は同じようにみんな見えますが、鍛冶屋さんによって癖のようなものがあるんやね」
まっすぐな包丁であることは、切れ味のよい包丁の条件である。鍛冶屋の仕事とは対照的に、研師の仕事は繊細な調整作業が繰り返される。ここでも注意されるのは温度だ。砥ぎによる摩擦で熱が刃に伝わってしまうと切れ味に影響をおよぼすという。
最後に砥石で仕上げる。天然の砥石がやはりいいのだが、生産量が減少しているため、人造砥石を使うことが多い、とのこと
「研いでいる面は目には見えないので、それを感じることが重要。目に見えないから指先のセンサーで感じる、言うことやね」
将来に向けての問題はやはり後継者不足ではないか、と言う。
「うちは幸いなことに継いでくれてますけど、これから少しずつ減っていくんじゃないですか? 大昔の話ですが、年に一回、仕事はじめにあわせて包丁を新調するというお客さんがおりましてね。ある時、忙しくて不本意な仕事をしたものを届けてしまったことがあったんですわ。そしたら、その人にはすぐに『なんや、これは!』とすぐにバレまして、えらく反省しました。そういった使い手の付き合いいうのも、なくなりつつあるように思います」
最後の歪みをとる調整。写真には収まっていないが、視線の先は包丁の歪みがわかりやすいように黒い板(紙?)だった。こうして調整された包丁が繊細な日本料理を支えている
研ぎあげた包丁は和泉利器製作所に運ばれる。ここで柄をつけて完成か、とおもいきやそうではない。ここでも届いた刃のわずかな歪みを矯正していくのだ。信田専務が積み上げられた商品を前に説明してくれた。
「研師がなおしてますけど、あわせの包丁はやっぱり歪みが出てくるものなんです。本焼きはそうでもないんですけど、そこを調整します。それから最低でも一年、長いものだと五年くらい寝かせます。寝かせることで金属を安定させるわけです」
飲食店で働く人は増えてもプロ用の包丁の需要が増えない
卸しメーカーは商品のプロデューサーであるだけではなく、高い品質を守るために細心の注意を払っている。効率が悪い気がするが、分業制は多くの人の手を通ることにより、粗悪な品が出てくるのを防ぐシステムであり、それが堺の包丁の質を保証してきたという側面はある。
「そやからうちは日本で一番在庫がある店違いますか」
冗談ではなく、真面目な口調で信田専務はそう言った。
和泉利器製作所の信田専務。ほがらかな大阪弁で、包丁について説明してくれた
「海外では日本の包丁の評価は定着してますね。僕もここがなければ海外で包丁屋をやったほうが儲かるんちゃいますか。でも、日本の包丁、言うて売ってるところもありますけど、経営してるのは中国人というケースもあるんで、例えば研ぐというところをはじめ、メンテナンスまでちゃんと情報発信できてないんです。そこのところは今後の課題ですね」
信田専務はスペインで開かれたマドリッドフュージョンという世界最大級の食の学会で、日本の包丁をPRしてきたばかり。歴史ある会社を引き継いでいくのは大変な苦労があると思う。
先にも触れたように、日本の包丁の需要が先細りしていっているという現状があるからだ。
飲食店で働く人は増えているのに
プロ用の包丁の需要が増えない現状
この箱に入っているのはすべて商品。そちらは写真撮影不可だったが、建物にはこんな風に在庫商品が並んだ棚がいくつもある
和包丁を家庭で見かけることはまずなくなった。かつては出刃包丁の一本くらいは家にあったのかもしれないが、魚を切り身で買ってくることが増えた今では家に備える必要性もないのだろう。
では、プロ用としての需要はどうか、というと、それも明るい材料はない。堺市が公表している数字によると平成18年度に9.31億円だった生産額は、平成20年度には6.1億円まで減少。わずか2年で3億円も数字が下がるということは相当なものだ。それにあわせて従業者数も332人から290人と減少している(堺刃物商工業協同組合連合会調べより)。深刻な不況で料亭などの閉店が相次いでいることなどが、その理由として挙げている。
総務省「経済センサス・基礎調査」によると飲食業界で働く人の数自体は増加している。にもかかわらずプロ用の包丁が売れないのは零細な小規模店が減少し、一店舗当り従業員の多い大型のお店が増えたことがその理由だ。セントラルキッチンなどを備えた店では必要なのはパックされた袋を切る『はさみ』くらいなのだろう。
例えば飲食店のなかでもっと早い速度で減少し続けているのは「すし店」である。反面、大型の回転寿司などは増加傾向にある、とのこと。回転寿司店などでは切られたネタを各店鋪に供給しているため包丁の必要性はやはり高くない。
後継者の問題等もあり、和包丁の未来は明るいものとは言えない。本連載のタイトルどおり、遺産化する日も遠くないかもしれない。業界全体の仕組みをどこかで変えていかなければならないのだろう。それも包丁文化を支える職人がもっと報われる形で。
包丁文化は単体では存続しえないもの
僕=樋口の意見としては、家庭に高級な包丁は必要ないと思う。それよりもきちんと研ぐことのほうが重要だ、という旨を記しておきたい。切れ味や使い心地といったものは主観的なものだが、そこそこの値段の商品なら上手に研げば、それなりの切れ味にはなる。ただ、高級な包丁は切れ味が長持ちするので、いいものを使うに越したことはないというだけだ。
そもそも包丁文化は単体では存続しえないものである。道具として包丁を使うには『研ぐ』というメンテナンス作業が必要だ。しかし、きちんと研いだ包丁を使っている家庭、あるいは飲食店がどれくらいあるか、というといささか心もとない。海外に向けての情報発信は課題だが、それ以前に足元が揺らいでいる感がある。
今回の包丁取材で僕の気持ちを明るくさせてくれたのは、普段、包丁の表に名前が出ることのない(もちろん伝統工芸士という立派な肩書を持つ人達なのだが)職人、鍛冶と研ぎ師の仕事だった。自らの仕事に誇りを持ち、手の内を隠すことなく披露してくれる人たちと接して、救われたような気がした。
最後になったが、原稿の細かな点について和泉利器製作所の信田社長より、ご指導から細かな修正の指示までいただいた。そんな経緯があったことと感謝の意をここで述べておきたい。