
2018年11月1日よりタイトルをWCA(世界の時事)に変更しました。
「くじらの町」
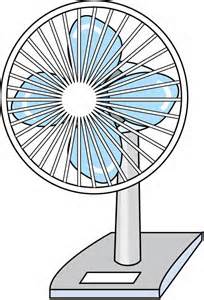 隠された“もう一つの歴史”…
隠された“もう一つの歴史”…
「移民の町」でもあった和歌山県太地町、カセットテープに残された悲痛な叫び
江戸時代以来、400年以上の捕鯨の歴史を誇る「くじらの町」和歌山県太地町。その一方で、明治から昭和にかけて大勢の町民たちが海外を目指した「移民の町」だったことはあまり知られていない。来年は「在米太地人会」が結成100年の節目を迎え、町でも“もう一つの顔”を現代に伝える動きが活発化している。町立石垣記念館には米国製の空き缶や豪州で実際に使われた潜水服などが展示されており、紀伊半島南端から夢を求めて太平洋や赤道を越えた当時のロマンが詰まっていた。
悲しい事故で捕鯨の危機…海外に活路を求めた
移民のきっかけは、現在でも地元で「背美(せみ)流れ」として語り継がれている悲しい事故だった。
明治11(1878)年12月24日未明、太地の漁師たちは、紀伊半島沖で発見された巨大なセミクジラ(背美鯨)の親子を追いかけていた。当時はかなりの悪天候だったが、この年は不漁続きで年越しもままならず背に腹は変えられない状況だった。死力を尽くしてクジラは捕獲したものの、船は激しい潮に流されて100人以上が命を落とした。この事故を機に、本格的な捕鯨は行われなくなったという。
しかし、太地の人たちは海を忘れたわけではなかった。明治から昭和にかけて全国的に労働力が余っていたことなどから、多くの日本人が米国やブラジルなどへ移住していった。昭和初頭に人口3800人に満たなかった太地町でも、500人以上の若者たちが米カリフォルニア州やカナダのブリティッシュコロンビア州、豪州ブルームに向かったといわれている。
太地町歴史資料室の櫻井敬人学芸員は「同じ魚を捕っても、日本と外国とでは値段が何倍も違った。能力を生かして豊かさを得るチャンスをつかもうとしたのではないか」と説明する。
米国産缶詰に刻まれた100年の歴史
町立石垣記念館では、町民たちが世界中の海で活躍した資料を展示する特別展「海を越える太地」が開かれている。
その中に少し変わった空き缶があった。古びた緑色の缶詰に「Chicken of the Sea」と印刷されている。直訳すれば「海の鶏肉」。1910年代から米国で広く食べられるようになった「ツナ缶」のことだ。米国に渡った太地の人たちは、脂分の少ないビンナガマグロからさらに脂を抜く技術を使って、米国人好みの淡泊な味に仕上げたという。
実は、このツナ缶、米国では現在でも販売されている。しばらく前に渡米した櫻井さんが、店頭に並んでいるのを見つけた。「ラベル表記も当時とそれほど変わっていなかった。ただし、中央に『100 YEARS』と書かれているんですよ」と興奮ぎみに話す。「太地の人が製造していたツナ缶が100年と、在米太地人会が来年に100周年を迎えることは偶然ではない」と指摘する。
太地町から米カリフォルニア州に移住し、いち早く漁業に取り組んだ日本人として知られるのが、漁野吉郎兵衛。ひ孫の清春さん(72)=埼玉県鴻巣市在住=は、親類が異国の地で暮らしていた当時のことは鮮明に覚えている。「子供のころ、米国から届く荷物にコーヒーやお菓子などが入っていて、とても楽しみだった」と振り返った。
司馬遼太郎の小説にもなった
カナダのブリティッシュコロンビア州では、1900年までの全漁業者約3700人のうち約2千人が日本人で、太地町をはじめとした和歌山出身者が多くを占めていた。彼らは漁の技術が優れていたため、川をさかのぼるサケや近海の豊富な水産資源を狙ったという。その一方で、女性たちは缶詰工場で働いた。特別展では、赤ちゃんを背負いながら異国の工場で働く様子を収めた写真も展示されている。
豪州ブルームへ移住した太地の人たちの生活の糧は魚ではなく貝だった。当時、貝殻を加工した洋服のボタンは欧米で人気が高く、多くが豪州産の真珠貝だったという。
太地の人たちは潜水具を身につけてひたすら貝を採り続けたが、長時間の潜水作業は危険を伴った。潜水病のほか、ホースを使ってダイバーへ送る空気がうまくいかなかったり、サメに襲われたりしたという。現在、ブルームの日本人墓地には潜水士を中心に約900人が葬られている。
櫻井さんは「日本人ダイバーの活躍はめざましいものだった。優秀なダイバーは3年で太地に家を建てたが、何度も命を落としかけたそうだ」と解説する。
作家、司馬遼太郎の小説「木曜島の夜会」では、紀伊半島南部からはるばる移住し、命がけで真珠貝を採取したダイバーの姿を描いている。
30年前に録音された祖母の肉声
「移民の町」としての太地町の歴史をどう伝えていくか。研究者だけでなく、住民自らが調査を行う動きも出てきた。
同町の木花(このはな)ひろみさん(60)は、昨年夏ごろから自分のルーツを振り返りたいと自宅の棚などに残る手紙などや、祖母のハナさんが生前に録音したカセットテープを調べ始めた。
昭和60年ごろに録音したとみられる60分テープが5本。録音当時は86歳。長年、米国に移住していたとあって、話は英語と日本語が混ざっていた。
そこには、米国へ移住後に仕事を求めて各地を転々とした日々のことがせつせつと語られていた。アラスカに定住するまでのことについて、それまで明るく話していたハナさんの話し声が急に暗くなったという。
「ピータースバーグに着いた日はクリスマスで、夜は雪が降りとても寒かった。われわれは持ち物が何もなかった」
木花さんは「おそらくクリスマスのお祝いをしていた家の横を通ったのかもしれません。祖母にとってつらい時期だったのでしょう」と当時の苦労に思いをはせる。その後、ハナさんらはサケやエビの缶詰工場で懸命に働き、後に経営を任されるまでになったという。
木花さんは「テープは聞きづらいですが、米国に住む親類らの協力を得て全部の内容を把握したい」と話している。
明治11年の「背美流れ」で一時は捕鯨から遠ざかった太地の漁師たち。その後、捕鯨技術の近代化で昭和11年には南極海に繰り出し、最盛期の昭和32年には220人以上がクジラを追った。
櫻井さんは「太地の人々の多くが外国に行っていた歴史を知ることで、自分のルーツを考えるきっかけにしてほしい」と話す。
急峻(きゅうしゅん)な紀伊山地と広大な太平洋に囲まれ、わずかな土地しかなかった太地町。捕鯨だけでなく、世界を舞台にたくましく生きた歴史があった。